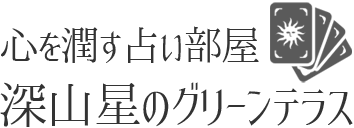講義のあとは池上本門寺ご参拝です。
久しぶりに訪れたお寺なので雨にも降られずにお参りできてうれしい限り。
まずは五重塔です。

近くには寄れないようになっています。
江戸時代幕府2代将軍徳川秀忠の乳母・岡部局の発願により、秀忠が1608年(慶長13年)に仁王門とともに寄進建立しました。江戸時代以来の度重なる火災にも消失を免れてきた五重塔です。
毎年4月第一土曜・日曜に五重塔まつり・特別開帳が行われています。
大堂(祖師堂)です。

鎌倉時代(1288年)に造立された日蓮大聖人尊像、第二祖日朗聖人像、第三世日輪聖人像を奉安するお堂です。
お線香の香りを身にまとわせてからお堂へ。お堂は16:00には閉まってしまうので足早に向かいます。こうしたお寺や神社もそうですが、閉まる時間を確認しておくのも大事ですよね。
それからお賽銭の準備。
すべてお札で用意する人はともかくとして、キャッシュレスの世の中です。
いざという時に小銭がまったくないということもあるので、小銭貯金などをしながらお賽銭を用意しておきましょう。
お賽銭大事です。
大堂を後にして、さらに北へ向かうと本殿(釈迦殿)に到着です。

本師釈迦牟尼仏・四菩薩・祖師像を奉安。昭和44年建立。外陣の仁王像はアントニオ猪木をモデルとしているそうです。


面影感じるかな?
本殿には入れず残念ですが、遠くからお師匠とともにお経をお唱えさせていただきました。
一人で読経と違って、みんなで読経というのもなんだか不思議なパワーがあるものです。
続いて、日蓮大聖人御廟所。

閉門されていました。
前回訪れたときも閉門してしまっていたのでなんとも縁のない場所です。
いつかはお参りできますように。
お次は大坊坂という階段を下っていきます。
その途中にあるのが多宝塔です。

天保2年(1831)の日蓮聖人550遠忌を記念して、日蓮大聖人御荼毘所(火葬された所)に建立。屋外に建つ宝塔形式の木造塔としては日本唯一の遺構。毎年10月のお会式に開扉されます。
階段をさらに下っていきますと、今回の旅の終着地に到着。
大坊本行寺・御臨終の間です。


池上宗仲公の邸宅跡。御臨終の間には日蓮大聖人がお寄りかかりになった柱を格護しています。毎年9月18日に宗祖御入山会が行われます。


駆け足ながらもじっくりお寺を歩くことができました。
案内付きなのでいつも以上に頭の中に歴史が入ってきた気がします。
良い体験になりました。